公式
https://www.terraform.io/docs/index.html
導入
https://www.terraform.io/guides/core-workflow.html
推奨方法
https://www.terraform.io/docs/cloud/guides/recommended-practices/index.html
https://www.terraform.io/docs/cloud/guides/recommended-practices/part1.html
https://www.terraform.io/docs/cloud/guides/recommended-practices/part2.html
https://www.terraform.io/docs/cloud/guides/recommended-practices/part3.html
https://www.terraform.io/docs/cloud/guides/recommended-practices/part3.1.html
https://www.terraform.io/docs/cloud/guides/recommended-practices/part3.2.html
https://www.terraform.io/docs/cloud/guides/recommended-practices/part3.3.html
https://www.terraform.io/docs/cloud/guides/recommended-practices/part3.4.html
チュートリアル
https://learn.hashicorp.com/collections/terraform/gcp-get-started
HCL
https://www.terraform.io/docs/language/index.html
CLI aka cmd(アルファベットリストから使う)
https://www.terraform.io/docs/cli/auth/index.html
GCP用リファレンス
https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/google/latest/docs
お便強
https://qiita.com/minamijoyo/items/1f57c62bed781ab8f4d7
https://qiita.com/donko_/items/6289bb31fecfce2cda79
https://www.apps-gcp.com/infra-automation-01/
https://colsis.jp/blog/gcpterraform/
Infra as codeとしてインフラの構築や設定をコード化できる
特にクラウドだと構築の自動化や構成管理等でのレバレッジが強力
■段階
Terraformとは?基本知識とTerraformのメリット4つを紹介 | テックマガジン from FEnetインフラ必要なリソースをTerraform化>workspaceの活用>main.tfの共通部分をmodule化
moduleは構成に合わないようなリファクタリングが必要になった時にterraform state mv が必要になってとたんにつらい、moduleを細分化しすぎるとvariable と output が大量に必要になって書きづらい、moduleは再利用できる複数のリソースの単位(プログラミング言語でいうところの関数みたいなもの)で作るのがしっくり
リソースの差分を無視するlifecycleブロックを使う
resource "aws_autoscaling_group" "app_1" {
name = "app-asg-1"
lifecycle {
ignore_changes = ["load_balancers"]
create_before_destroy = true//新しいのを作ってから古いのを削除
}
}
外部ファイルを文字列として読み込む
resource "aws_iam_role" "ec2_role" {
name = "ec2-role"
assume_role_policy = "${file("./ec2_assume_role_policy.json")}"
}
1つのディレクトリで複数のStateを扱うWorkspaceという機能もあるのですが、
個人的には普通にディレクトリを分けて管理する方が楽
production/stagingが完全に同じリソース構成で、設定のパラメータの差分がちょっとだけあるという理想的な世界ではWorkspaceでも運用できるかもしれませんが、現実的にはstagingだけリリース前の検証用の一時的なリソースが立ってたりとか、完全に同じ構成にならないことも多いので、モジュールの読み込みの有無や一部の環境だけ存在するリソースなどの差分を吸収できる場所があったほうが都合がよい
モジュールが公式から提供されている
Browse Modules | Terraform RegistryTerraform の terraform.tfvars とは | 30歳未経験からのITエンジニア (se-from30.com)環境情報は外部ファイルが基本
prd/stg/dev環境はprd.tfvars, stg.tfvars, dev.tfvarsを用意
.tfvars 各環境の設定
aws_access_key = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
aws_secret_key = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
aws_region = "eu-west-1"
main.tf
terraform {
required_version = "= 0.12.26"
}
provider "aws" {
version = "2.66.0"
access_key = var.aws_access_key
secret_key = var.aws_secret_key
region = var.aws_region
}
var.tf 空の受け皿
variable aws_access_key {}
variable aws_secret_key {}
variable aws_region {}
Terraform で変数を使う - Qiita実行時に-var-fileで値ファイルを指定して環境などを切り替えると良いかもしれない
terrafrom plan -var-file=dev.tfvars
terrafrom plan -var-file=prod.tfvars
変数ファイル指定がないときは変数でdefaultに入れておく、descriptionで変数の説明もかける
variable "foo" {
type = "string"
default = "default-var"
description = "Sample Variable"
}
変数ファイルを異なるバックエンド(フォルダ構成)で共有したいときはシンボリックリンクを貼る
ln -s ../common/shared_var.tf shared_var.tf
credentials等の秘匿したい変数を外部のファイルやコマンドライン引数から読み込む
variable "credentials_file" {} @var.tf 変数を定義し空にしておく
credentials = file(var.credentials_file) @main.tf ファイルを読むがファイル名は変数
terraform plan -var 'project=
' -var 'credentials_file=.json' @cmd プロジェクトとクレデンをコマンド時に指定
他にもvars.tfvars設定ファイル(行頭variableが不要)、TF_VAR_環境変数による指定-var-fileで変数ファイルを明示してcmd、ファイル名は.tfvars/.tfvars.json
-varで変数を明示してcmd
順序があり後の読込でオーバーライド
↓
HCLの変数は基本2種類のlocalとvariable
variableはグローバル変数、ファイル外やコマンドラインから使える
その他の変数参照方法としては(上から優先に適応)
コマンド引数 一時的に使用
変数ファイル terraform.tfvars git管理等で外部ファイルで?
環境変数 TF_VAR_ 実行ログに残らない鍵情報等
workspaceは使わない、moduleを限定的に使う
設定をコード化>Gitレポジトリに置く>設定内容、作業履歴の明確化、チームでの運用性向上
■特性
TFの影響を反映するのはterraform applyの時だけ、tfファイルとtfstateの差分を実際にリソース作成する
tfファイルで変更した場合、TFはリソースの再作成を行うので一度消えることになる(大体は単位が権限だったりで影響がないだけでplanで要注意)
terraform planはtfとtfstateと実体の差なので、実体があってもtfstateになければwill be createdでplan時は表示される
terraform importはtfファイルからtfstateへ記載だけを行う(実体からも情報を取得しtfstateに入れる)
カレントdirの全.tfファイルor.tf.jsonを評価するのでtfファイルの名は何でもいい
各リソースに対してTF化するかは選択ができるが、TFする場合はそのリソースに必要な全記載をTFファイルに行う
terraform import tfResourceID.yourResourceName gcpIdentifier のコマンド
terrafrom import google_bigquery_dataset.tf-1 bangboo-prj/test-dataset
tfResourceID(リソースIDというようタイプ:リソース種別)はTF指定のもの、yourResourceName (リソース名)は任意のもの
構成ファイル.tfはローカルのものが使われる、importするとtfstateに反映
GCP identifierはTF公式サイトの各サービスの一番下import項目を見ると指定内容が分かるのでGCPを見て拾ってくる
terraform state list TF化されているリソースを見る
terrarorm apply時にもtfstateは更新される(オプション-refresh=falseで無効可)
またapply時に-target=xxxでデプロイするリソースを特定できる(TFファイルだけでなくTFステートもターゲットになる)
resource "google_sql_database_instance" "instance" {
provider = google-beta
name = "my-database-instance"
}
resource "google_sql_database" "db" {
instance = google_sql_database_instance.instance.name
name = "db"
}
ToSetは値設定をするが順不同で重複を省く
resource "xxx" "aaa" {
for_each = toset(["foo", "bar", "bar"]) でbar, foo
name = each.key
}
for_each/eachのループ
locals {
sg = {
foo = "FOO"
bar = "BAR"
}
}
resource "xxx" "aaa" {
for_each = local.sg
name = each.key
description = each.value
}
mapをリストしたものをfor_each
locals {
images = [
{ name = "foo", image = "alpine" },
{ name = "bar", image = "debian" },
]
}
resource "docker_container" "this" {
for_each = { for i in local.images : i.name => i } # こう書くのが正しい
name = each.value.name
image = each.value.image
}
terraform importはリソース単位、更新はできず削除してから追加 terraform state rm google_bigquery_dataset.tf-1
実設定とimportの内容が違う場合は実設定の情報でtfstate化されるようだ(importは項目を入れ込む感じ?)
なので実環境に変更を加えるにはterrafrom apply、tfstate化もされtfファイル/tfstate/実設定の3者で同じになる
apply時にtfstateと実設定が違う場合、例えば既存設定がある場合は重複エラーになりapplyできず、importしtfstateと実設定を同じにしてから、tfファイルの内容をapplyすることが必要
terraform importで対象プロジェクトを間違えるとハマる
通常のterraform applyではproviderの情報を使用してプロジェクトを決めるが、importはハードコードするのでimportを間違えばなぜ変な変更がでるのかわからなくなる(プロジェクトが変なものはstateを調べ、terraform state rmするしか)
■セットアップ
作業ディレクトリの作成(プロジェクトに対するローカルのフォルダ)
プロバイダを指定したtfファイルの作成(gcsにstateを置く設定が良い
provider "google" {
project = "bangboo-kuso"
}
terraform {
backend "gcs" {
bucket = "bangboo-kuso-terraform"
}
}
terraform init ローカルに対して初期化
プロジェクトレベルownerのサービスアカウントを持っておく
セットアップする際にtfsateのbackend保存場所のbucket部分をコメントアウト
bucketを作るterraformを実施しbucketを作成しつつlocalにtfstateファイルを作成
再度terraformをするとtfstateファイルがbucketにコピーされる
bucket部分のコメントアウトを外すと次回tfからはバケットにtfstate更新する
このときローカルtfstateの内容をバケットに写すか聞かれるが写す
(写さないと差分しかバケットに行かないのでimport等が必要になる)
■既存リソースのTF化のおおよその作業
リソースタイプと名前を定義したtfファイルを作成する(任意のリソース名、基本ユニーク、纏められるものは重複してもいい)
resource "google_cloudfunctions_function" "fuckin" { ... をtfファイルに記載
tfResourceID(リソースIDというようタイプ:リソース種別)とyourResourceName (リソース名) だけで
リソースタイプや個別パラメータは公式ドキュメントを参照しながら定義
https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/google/latest/docs
(簡単)tfファイル内で1行目以外は空で、terraform planをするとエラーで必要なものが分かるので、それを埋める
planが通ると自動的に値をサーバから拾ってくる(importすればtfstate.tfに入っている or コピーしてTFに入れる)
planでダメならterraform state show tfResourceID.yourResourceName でstateを見てtfファイルにパラメータを定義していく
暫定に空でリソースをTFファイルに記載しterraform import、次にtfstateを調査する
terraform state list tfstateファイルにあるアセットを一覧
terraform import google_bigquery_table.xxx project/dataset/table インポート
terraform state show google_bigquery_table.xxx tfstateの該当部を表示
terraform state rm google_bigquery_table.xxx インポート取り消し
TF定義は複数の方法がある、最終GCP公式のRestAPIで確認するしか
terraform importする(公式ドキュメントの一番下にimportコマンドの指定がある)
terraform planして差分がなくなるまでtfファイルを修正する
import(tfstate)の修正は一度stateから削除する terraform state rm google_bigquery_dataset.tf-1
(既存リソースがあってもあくまでtfファイルとtfstateの差分なのでinitした状態でplanしてもup-to-dateと表示されるだけ)
tfstateファイルにおかしなものが無いか確認、keyとか含まれないか
■個別
リファレンスでoptionalとなっていてもtfファイルでは必要な場合もある
tfstateファイルからは必要ないとして自動的に削除されるが
スプシをBQでみれるFederatedQueryはテーブルだけ定義しimportしstate show調査
urlをTFファイルに記載する
シャーディング(日付別)テーブルは定義できないのでは
生成するクエリの方をTF化したい
Authorized viewはモジュールがあるがconflictがあり全消えする場合がありTF化にまだ向かない
google_bigquery_dataset_iam_memberでもAuthorized viewをはがしてしまう。
Authorized viewを使っている個所は google_bigquery_dataset_access あるいは google_bigquery_dataset の access フィールドを使う。
google_bigquer_dataset_iam_policy と google_bigquery_iam_binding は Authoritative で権限追加でなく権限強制設定でコンソール付与分を引き剝がすので、使わない方が安全。
なお、Authorized view と Routines はTerraform化できない事が分かっている(2022/4時点)
ScheduledQuery は Terraform化できるが実行者の設定ができない(Terraform実行者がSQ実行者?誰?)
BQ関連ではデータセット定義、テーブル定義、ビュー定義、フェデレテッドクエリ定義、ScheduledQuery定義をTerraformで行い
BQ権限定義、AuthorizedView定義、Routines定義は行わない
BQ権限を定義するならデータセットレベルはgoogle_bigquery_dataset_access
プロジェクトレベルはgoogle_project_iam_memberで実施すると別なので安全らしい?
■TF公式ドキュメント
google_organization_iam_custom_role | Resources | hashicorp/google | Terraform Registrygoogle_organization_iam | Resources | hashicorp/google | Terraform Registryカスタムロールを設定して、組織レベルのIAMでそれを使いたい
TFのorg_iamページのArgument referenceのrole項目を見ると
Note that custom roles must be of the format organizations/{{org_id}}/roles/{{role_id}}
TFのorg_iam_custom_roleページのAttributes referenceのrole項目を見ると
id - an identifier for the resource with the format organizations/{{org_id}}/roles/{{role_id}}
で下記と分かる、使用側と被使用側のTFマニュアルを両方確認する
resource "google_organization_iam_custom_role" "my-custom-role" {
role_id = "myCustomRole"
org_id = "123456789"
title = "My Custom Role"
description = "A description"
permissions = ["iam.roles.list", "iam.roles.create", "iam.roles.delete"]
}
resource "google_organization_iam_member" "my-organization" {
org_id = "123456789"
role = google_organization_iam_custom_role.my-custom-role.id
#あるいは通常"roles/bigquery.dataEditor"のようにいれるがorganizations/0123456789/roles/chinkoといれる
member = "user:jane@example.com"
}
↑
resourceの2番目リソース名を定義しますが任意の名前を指定します
ここが同じ項目はユニーク制限がない場合は追加としてまとめられます
通常はユニークにしterraformで管理するリソース名(yourResourceName)を宣言します
※1番目のリソースタイプ内でユニークにするのが基本(全体でもユニークの方が分かり易い)
TFファイルに定義をしたい →定義したいリソースのArgument referenceの項目を設定
TFファイルに定義した内容を変数で使いたい →使いたいリソースのAttributes referenceを見る
terraform importしたい →インポしたいリソースのページ一番下のimportコマンドの指定を見る
■他に一般的なTF(既存がimportされると以下で変更をapplyして運用)
terraform -v 稼働確認
terraform fmt ファイルの記述フォーマットを整える
terraform validate ファイルの検証
terraform plan アクションを計画
terraform apply 最後に変更を適応
terraform show ステータスを確認、一覧
terraform destroy で簡単にインフラの吐き、initができないとき必要そう
■特定のリソースだけ適応したい
terraform plan -target="tfResourceID.yourResourceName"
terraform apply -target="tfResourceID.yourResourceName"
TFファイルだけでなくTFステートもターゲットに含まれる
これでTFファイルにコードがなくTFステートだけにあるものを指定して削除等もできる
■terraformのバージョン管理
.terraform.lock.hclファイルでGCP provider等のライブラリのバージョン管理をしている、pyenvのPipfile.lockみたいなHash差分が記載されている、terraform init等で生成されapply時の設定が担保される、通常tfファイルでproviderのバージョンを記載すればよいので不要と思われる
.terraform-versionファイルでterraform自体の要求バージョンを担保できる
通常はtfenvを使えばよい、tfファイルでrequired_versionを記載すればよいので不要と思われる
■tfenvを使う場合
tfenv install 1.0.0
tfenv list
tfenv use 1.0.0
terraform init
terraform workspace list
terraform workspace select ore_space
main.tf作成し記載
terraform fmt tfファイルのフォーマット(書式は適当で書けばいい)
gcloud auth login ローカル操作のための認証
gcloud auth application-default login SDKを実行のための認証
API&Servicesでクレデンシャルは取得できそう、key=xxxx
既存のリソースを調査
terrafrom import google_storage_bucket.pri-bucket project-abc123/asia-northeast1/pri-bucket でimportとか
terraform refresh tfstateの最新化、どのタイミングで使う?
■既存のリソースを調査
terraformer import google --resources=instances,forwardingRules --regions=us-west1 --projects=xxxx-123 とか
既存リソースimport
https://www.apps-gcp.com/terraformit-gcp/
ダメなら terraform state rm で不要分を削る
新環境用にtfファイルを準備
新環境で下記を実行
terraform init
terraform state push xxx.tfstate
terraform planで差分がないことを確認
■GCP権限(メールの変名時)
GCPはGWS gmailメールの変名に追従して権限も付与状態も変化がない
しかしterraformは追従しないためtfファイルで使っている場合は変更する
■gcloud cmd
https://www.devsamurai.com/ja/gcp-terraform-101/
gcloud projects list 権限あるプロジェクトを表示
gcloud config set project [prjID] ワーキングプロジェクトの設定
gcloud services enable iam.googleapis.com サービスの有効化
gcloud iam service-accounts create terraform-serviceaccount \
--display-name "Account for Terraform" サービスアカウント作成
gcloud projects add-iam-policy-binding [PROJECT_ID]
--member serviceAccount:terraform-serviceaccount@[PROJECT_ID].iam.gserviceaccount.com --role roles/editor 権限付与
gcloud iam service-accounts keys create path_to_save/account.json
--iam-account terraform-serviceaccount@[PROJECT_ID].iam.gserviceaccount.com クレデン発行
■プロキシを入れないとアクセスできない、が同セグメントは不要なためno proxy設定する
Linuxの場合
export http_proxy=http://proxy:3128
export https_proxy=http://proxy:3128
export no_proxy=localhost,127.0.0.1,.in-xxx.com
コマンドプロンプト
set http_proxy=http://proxy:3128
set https_proxy=http://proxy:3128
set no_proxy=localhost,127.0.0.1,in-xxx.com
PowerShell
$env:http_proxy="http://proxy:3128"
$env:https_proxy="http://proxy:3128"
$env:no_proxy="localhost,127.0.0.1,in-xxx.com"
■ncコマンドでプロキシ確認
自分の環境から環境用のproxy に接続できるかどうか?
apt install netcat-openbsd
nc-vz. proxy 3128
でプロキシ確認
nc-vz 127.0.0.1 20-100
自分自身に対してTCP20~100番ポートをスキャンし成功するとsucceed!!
cnc-likすると簡易的に好きなポートでサーバーを起動できる
特定のボートの疎通確認などに
nc-lk 8000
-l オプション:サーバーモードで指定したポートで接続を待ち受ける
特権ポート (0-1023)までは、名前の通り特権が無いと、コマンドが通らない
-kオプション:接続が終了してもプロセスを終了せず継続し新しい接続を待ち受ける
レスポンスのデータを見たいなら、python モジュール等で
python3-mhttp.server 8080
■LDAP mgrとLDAP
■sudoers について
どのユーザやグループがどのsudo コマンドを利用することができるのかの定義の記載があり、ユーザとグループの設定で権限を制御
どのユーザがどのsudo コマンドを利用することができるのか $sudo -l
■Linux terminal
tabで入力補完
↑↓で入力履歴呼び出し
^qはCtrl+qを押すという意味
半角/全角キー 日本語を切り替える(画面右上にもIMEがある、win+spaceの場合も)
ls -la ディレクトリ内を表示
ls -a 隠しファイルを含み表示
(GUI)ctl+h 隠しファイルを表示(メニューでもチェックで可)
pwd 現ワーク中のディレクトリを表示
cd ../ 上に上がる
clear 表示内容を消す
mv beforeName.text afterName.txt ファイル名変更
rm -R ディレクトリ名 削除、ファイルはrm a.txt
ls -l > hoge.txt >結果を上書き
ls -l >> hoge.txt >>結果を追記
printenv 環境変数表示 printenv xで特定表示
grep aaa -rl ./ カレントディレクトリ以下からファイル内にaaaが含まれるファイルを検索
grep -R $keyword *.py .pyファイルからkeywordを検索
sudo - 一般ユーザが特権操作する sudo省略
sudo -i rootに切り替える
sudo -iu <username> 特権ユーザ切り替え
テキスト選択
Shift↑or↓ で行全体
home(+fn)で行頭、end(+fn)で行末移動
nano text.txt 作成あるいは開く、nano簡単かも、画面下コマンドでctrl+?すればいい
コマンドM-UはEsc+u
ctrl+k で1行削除
$()
ドル記号と括弧で囲んだコマンドは実行結果を出力し展開
echo "現在のディレクトリは、$(basename $(pwd))です"
パッククォートは囲った中身をコマンドとして実行しその結果を出力
echo "今日は、`date +%m月%d日`です。"
変数と$()とバッククォートを使ってワンライナー
■viエディタ
sudo apt install vim
vi text.txt ファイル作成あるいは開く
viは2つ+αのモード
┣コマンドモード
┃┗コロンモード(exモード:祖先のラインエディタ)
Escでコマンドへ抜ける
┗挿入 i (入力モード)
ファイル名を指定し保存 :w new_file_name.txt
強制保存のコマンド :w!
保存せず終了 :q 強制終了 :q!
:10 10行目に移動
:set number 行数を表示
:num 現在のカーソル位置行数を表示
クリップボードをペースト iで挿入モードに入り Shift+Insert
vi内でコピペ:yコマンドのコピー、pコマンドのペーストなので下記の様にする
2yw ならカーソルから2単語コピーされます
3yl ならカーソルから3文字コピーされます
y$ ならカーソルから行末までコピーされます
p ならカーソルの後ろにペーストされます
$ カーソルを行末へ
G カーソルを最終行行頭へ
- 前行の行頭へ
Enter 次行の行頭へ
w カーソルを1語進める
b カーソルを1語戻す
Ctrl-d 1/2画面下へ(down)
Ctrl-u 1/2画面上へ(up)
Ctrl-f 1画面下へ(foward)
Ctrl-b 1画面上へ(back)
/文字列(Enter要) 文字列検索(スラッシュ)
┣n 次の検索文字列へ
┗N 前の検索文字列へ 保存して終了 :wq 保存して強制終了 :wq!
■環境変数は下記の順で探す、なので必要なら下位のものを上にコピー
~/.bash_profile
~/.bash_login
~/.profile
source ~/.bash_profile 編集したbashrcをbash_profileに反映させる
bashrcはbash起動毎、bash_profileはログイン毎
■SSHの設定
Linuxコマンド【 ssh-keygen 】認証用の鍵を生成 - Linux入門 - Webkaru$ ssh-keygen
パスフレーズは空でも設定上は問題ないが塩っ気が足らん気が
秘密鍵(id_rsa)と公開鍵(id_rsa.pub)が生成され、ホームディレクトリに作成される
/home/yourID/.ssh/id_rsa
/home/yourID/.ssh/id_rsa.pub.
公開鍵をSSHサーバや外部サービスに登録する等して使う、秘密鍵は明かさないこと
$ vi ~/.ssh/config
Host oketsu
HostName 1.XXX.XXX.XXX
User hoge
IdentityFile ~/.ssh/id_rsa.pub
LocalForward 5912 localhost:5902
ProxyCommand connect-proxy -H proxy.syanai.in:8022 %h %p
Host github.com
HostName ssh.github.com
Port 443
IdentityFile ~/.ssh/id_rsa.pub
ProxyCommand connect-proxy -H proxy.syanai.in:3128 %h %p
User githoge
$ chmod 600 .ssh/config
下記のように実行すると、ログイン/GITできます。
$ ssh oketsu
$ git clone githoge@github.com:kusogitry.git
$ id 所属グループ等を表示
$ uname -n;id;date
■NW設定
/etc/resolve.conf
nameserver 88.88.88.88
~/.profile とか .bashrc とか
export http_proxy=http://proxy/3128
/etc/apt/apt.conf
ip addr
| レイヤー | 名称(日本語) | 主な役割 | 主なプロトコル・規格 |
|---|
| レイヤー7 | アプリケーション層 | アプリケーションごとの固有の通信規定 | HTTP / SMTP |
| レイヤー6 | プレゼンテーション層 | 文字コードやデータ形式など、情報の表現方法を規定 | MIME / SSL |
| レイヤー5 | セッション層 | 通信の開始・維持・終了など、通信セッションの管理 | ソケット |
| レイヤー4 | トランスポート層 | データ転送の信頼性や誤り訂正などを規定 | TCP / UDP |
| レイヤー3 | ネットワーク層 | 異なるネットワーク間の通信方法を規定 | IP / ICMP |
| レイヤー2 | データリンク層 | 同一ネットワーク内での通信規定 | Ethernet / PPP |
| レイヤー1 | 物理層 | ビット列を電気信号など物理的な信号に変換する規定 | 1000BASE-T / 802.11 |
プライベートIPアドレスのクラス分け| クラス | アドレス範囲 | CIDR表記 |
|---|
| クラスA | 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 |
| クラスB | 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12 |
| クラスC | 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16 |
■スクリプト実行
nohup python3 main.py & ユーザディレクトリにnohup.outログが実行完了時に一度に保存される(重いと思われる)
nohup python3 main.py > /dev/null 2>&1 & ログなし
nohupはバックグラウンド実行、ログアウトしても実行続ける
jobs ジョブリストを出す
fg ジョブ番号 フォアグラウンド実行に変える
bg ジョブ番号 バックグラウンド実行に変える
ctrl c キャンセル
ctrl z 中断(再開できる)
crontab -e 編集
crontab -l 確認
sudo service cron restart 再起動
systemctl status cron 稼働の確認
30 12 * * 0 python3 /home/app_hoge/main.py
cronはバックグラウンド実行でnohup &を含めると実行されない、多分
top プロセス/CPU/メモリ等の情報、こちらで動いていればpsのstatがsでも問題ない、多分
ps aux
ps f -A プロセスをツリーで表示し便利
kill -l
kill -SIGCONT プロセス番号
sudo less /var/log/cron.log
sudo tail -f /var/log/cron.log
sudo less /var/log/syslog
sudo tail -f /var/log/syslog
■ディスク系
ext4 一般的なデスクトップやファイルサーバ向け、16TBまで、ファイルシステムチェックで遅い
xfs 高負荷IOで大容量データ処理向け、ジャーナルなし、ファイルシステムチェックを短縮
論理ディスク=パーティション
/dev/sda1, /dev/sda2, /dev/sdb, /dev/sdf等、数字はパーティション番号、数字がないとパーティション1つだけ
ディスク拡張
lsblk
df -Th
du -sk * | sort -nr
#xfsの場合
pvdisplay
pvresize /dev/nvm
vgdisplay
lvdisplay
lvextend -l +100%FREE /dev/vg001/lv001
xfs_growfs /opt
#ext4の場合
apt autoclean キャッシュあるがインストールされていないdebファイル削除
apt autoremove 必要なくなったパッケージ削除
disk -l /dev/nvm パーティション情報
growpart /dev/nvm 1 指定パーティションの容量拡張
resize2fs /dev/nvm ファイルシステム拡張
容量調整
/var/cache はapt-get clean, yum cleanで消す程度で
■swapをrootからvarに移動
free
swapon -a
swapを無効化
swapoff -v /swap.extended
swapをvarに移動
mv /swap.extended /var
/etc/fstabからswapのエントリを/varに書き換え
cat /etc/fstab
swapを有効化
swapon -a
確認
free -h
■ライブラリアップデート
sudo apt update
apt list --upgradable | grep mysql
sudo apt install mysql-client=6.6.6-0ubuntu2.1~99.99.9
sudo apt install mysql-client-core=6.6.6-0ubuntu2.1~99.99.9
…
dpkg-l | grep mysql
■WSL2
https://qiita.com/zakoken/items/61141df6aeae9e3f8e36
https://qiita.com/SAITO_Keita/items/148f794a5b358e5cb87b
WSLインストール後はネットワークの設定が必要なら
例) apt updateが出来ない
WSL のバージョンはユーザの設定依存のため、version 2 (WSL2) が必要ならコマ ンドプロンプトで以下のコマンドを実行
wsl --set-default-version 2
アプリからWSL起動、CMDやPowershellならwslで起動 wsl --shutdown で停止 設定したユーザディレクトリにアクセスする(それぞれ別の場所)
• WSLからは /mnt/c -> /mnt/c/Users/ore/Desktop/github
• WINからは \\ws/$ -> \\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\ore
NW設定: WSL2のデフォルトでは起動するたびにWindowsホストのDNS設定を基にして自動的に/etc/resolv.conf を生成するが、サーチリストはWindows側から引き継がれないうえ、意図しないタイミングで勝手に再生成されてしまうので停止する
nano/etc/wsl.conf
下記追記
[network]
generate ResolvConf = false
DNS設定
sudo unlink /etc/resolv.conf
sudo nano /etc/resolv.conf
以下のように設定
nameserver 172.27.117.yy
nameserver 172.27.117.xx
search in-xxx.com dns search list.xxx.com
proxy設定
nano-/profile
以下の設定を既存プロキシの下に追加
export http_proxy="http://proxy:3128"
export https_proxy="http://proxy:3128"
apt の proxy 設定
sudo /etc/apt/apt.conf
以下のように設定
Acquire: http: Proxy "http://proxy:3128",
Acquire: https: Proxy "http://proxy:3128";
WSL2を抜け、WindowsコマンドプロンプトでUbuntu を再起動
ore@unco-017:/mnt/c/Users/ore$ exit
rootでキーを作成するとgithub上でユーザがrootとなる
sudo adduser aaa
sudo usermod -aG sudo aaa
sudo nano /etc/wsl.conf 下記を追記しwsl再起動
whoami
[user]
default-aaa
echo $HOME
cd-
mkdir.ssh
ssh-keygen sudoだとgithubログイン時に名前がrootになってしまう
/home/aaa/.ssh/id_rsa
cd- /home/aaa
nano/home/aaa/.ssh/config
Host github.com
HostName ssh.github.com
Port 443
ProxyCommand connect-proxy -H proxy:3128 %h %p
user git
chmod 600 config
eval "$(ssh-agent-s) sshエージェント起動
ssh-add/home/aaa/.ssh/id_rsa sshエージェントに鍵を登録
ssh-add確認
初回は接続yesをして Warning: Permanently added (ssh.github.com): 443 (ED25519) to the list of known hosts.
wal-d Ubuntu-22.04 -u root パワシェルでrootユーザに切り替える場合
wal.exe-shutdown パワシェルでシャットダウンや再起動の場合
パッケージの更新
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
WSL環境設定
cd /home/ore
は/rootを表す(/homeでない)
sudo apt install connect-proxy
/rootにキーを生成
ssh-keygen
passphrase xxXX
cat /root/.ssh/id_rsa
nano/root/.ssh/config
Host github.com
HostName ssh.github.com
Port 443
ProxyCommand connect-proxy -H proxy: 3128 %h %p
user omeco
chmod 600 config
シンボリックリンクを生成する
cd /home/ore
In-s-/ssh
Githubサイトのユーザ設定でpub keyを登録し、承認する
cd /mnt/c/Users/ore/Desktop/github
git clone git@github.com:oreore/xxx.git
ping github.com で通信確認ができる
curl https://sdk.cloud.google.com | bash
exec -1 $SHELL
gcloud auth application-default login
URLコピペ
gcloud config configurations list
gcloud config configurations create kuso
gcloud config set account xxx@xxx.com
gcloud config set project project-x
gcloud config configurations activate kuso
gcloud auth login
pyenv install 3.13.0
pipenv-python 3.13.0
gcloud components update
gcloud components install cbt(BigTable例)
(パスフレーズを省略できる) eval $(ssh-agent); ssh-add-/.ssh/id_rsa
tfenvをマニュアルインストール https://github.com/tfutils/tfenv
tfeny install 1.00.0
tfenv list
tfenv use 1.00.0
export TF_CLI_ARGS_plan="-parallelism=50"
export TF_CLI_ARGS_apply="$TF_CLI_ARGS_plan"
環境変数を変更した場合は source ~/.bash_profile を反映
■SPF
spfレコードはメールを送信する際、送信元サーバとDNS上のIPアドレスを比較
自社から取引先に送信したメールにSPFレコードを設定していなければ、相手側のメールサーバで迷惑メールとされ届かない場合も
送信元のDNSに送信元IPをSPFレコードに登録する(ドメインをSMTPのIPに変える?
ドメイン IN TXT v=spf1 ip4:172.16.0.1 -all
(+が省略されているがIP許可、allを認証しないという意味)
送信側SMTPサーバではSPFをチェックせず何でも送信
受信側MTAにて設定され(SMTPにはトランスファのMTA、デリバリのMDA
spfを使えば先方がspfレコードを登録していなければメールが受け取れない
postfixやeximのSPFをonにする設定がある
spfレコードが設定されているかを確認
=============
■VS code
マルチカーソル:ctrl+shift+↓
[Alt]+クリック | カーソルを追加 |
[Ctrl]+[Alt]+[↑]/[↓] | カーソルを上下に追加 |
[Ctrl]+[U] | カーソル操作を元に戻す |
[Shift]+[Alt]+[I] | カーソルを行末に追加 |
[Ctrl]+[L] | 行を選択 |
[Ctrl]+[Shift]+[L] | 選択中の文字列と同じものをすべて選択 |
[Ctrl]+[F2] | カーソル位置の単語と同じものををすべて選択 |
[Shift]+[Alt]+[→] | 選択範囲の拡大 |
[Shift]+[Alt]+[←] | 選択範囲の縮小 |
[Shift]+[Alt]+ドラッグ | 矩形選択 |
[Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[カーソル] | 矩形選択 |
[Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[PgUp]/[PgDn] | 矩形選択 ページ上下 |
VSCodeのマルチカーソル練習帳 - Qiitaマルチカーソルを使わないVSCodeはただのVSCodeだ!〜解説編〜 - memo_md (hateblo.jp)続き
/// BANGBOO BLOG /// - Linux cmd2■Big queryリファレンス
BigQuery解説:https://beyondjapan.com/blog/2016/03/what-is-bigquery/
クエリ処理のツリーアーキテクチャによる分散並列処理
複数のサーバーに対してツリー状に拡がっていき、並列にサーバー上で同時に分散処理
ルートサーバ>intermediateサーバ>leafサーバ
BigQuery MLという機能を利用すると、機械学習モデルをCloud AI PlatformのTensorFlowなどに連携させ、クエリ結果を素早くAIと連携
Lookerというデータ分析プラットフォームとの連携よりクエリ結果を、データ統合、変換、分析、可視化、レポーティングすることができ、非常に強力なBI
列指向型・カラム型データベース・カラムナストレージ(一般的なRDBMSでは行単位でデータが保存)
必要なカラムのデータを取得するだけでよく、またデータは圧縮できる
https://dev.classmethod.jp/articles/google-bigquery-debut/
GCPプロジェクト>データセット>テーブル(行row列columnで普通のテーブル、ネイティブbigqueryテーブル/Googleドライブのような外部テーブル、SQLクエリによるビュー)
アンスコ_で始まるデータセット名は隠しでコンソールで非表示
ジョブは非同期で実行され、ステータスをポーリング(データの読み込み、データのエクスポート、データのクエリ、データのコピーなど)
クエリ(ウェブ UI、bq コマンド、BigQuery REST APIの方法がある、SQLと同じ?
SELECT title, answer_count, view_count
FROM `bigquery-public-data.stackoverflow.posts_questions`
ORDER BY view_count DESC LIMIT 10
BigQueryはSELECT tag, time FROM [dataset_name.table_name_20151206]のように必要な列だけを選択した場合にはスキャンの幅を狭めることは可能ですが、LIMITやWHERE句には何を書いてもテーブルをフルスキャンしてしまう
節約 Amaのs3に入れRedshift内でテーブルを分割した後にBigQuery
Hadoopでも使われていたGoogle開発のエンジンであるMapReduceは、非構造化データをプログラミングモデルを通して扱うが、巨大なテーブルの結合や巨大な出力結果のエクスポートも可能である半面、処理時間は数分間から数日に及んだ、だが、BigQueryは、あらかじめデータを構造化してBigQueryのテーブルに格納しておかねばならないが、ほとんどのクエリは数秒で完了する
サードパーティ ツール(データの読み込みや視覚化を行うツールなど)を使用して BigQuery のデータにアクセス可
Google Cloud SDKをインストールすればコマンドラインが使える
BQは同一リージョンでないとJoinができない、ゾーンはマルチで良い
BQでは us と eu がマルチリージョン
22/4現在のリージョンリスト:asia-east1-2、asia-northeast1-3、asia-south1-2、asia-southeast1-2、australia-southeast1-2、europe-central1-2、europe-north1、europe-west1-6、northamerica-norhteast1-2、southamerica-east1、sourthamerica-west1、us-central1、us-east1-4、us-west1-4
`other-prj`.dataset.table あるいは `other-prj.dataset.table`
■標準SQL
先頭行でレガシーか宣言 #standardSQL あるいは #legacySQL
バッククォートでエスケープ、プロジェクト区切りも.(ドット)、From句のカンマはCross joinで全組合せかと思われ通常通りjoinやunionを使う事
配列が使える、カラム一つに配列を入れて多元的に扱える
withで一時テーブルを作れる
exceptでカラムを除外、replaceでカラムの置き換え
select * except(kuso) from a
分析関数over()とwindowで計算ができる
rank() over (order by x)は下記moreのRFMに使用している
ROW_NUMBER() over (order by timestamp) as id,で採番できる
地理関数とかJSON関数とか色々関数もありそう
■レガシーSQL(標準SQLを使うのが由)
予約語は角かっこを使ってエスケープ、プロジェクト区切りは:
集計関数で WITHIN キーワードを使用すると、レコード内の繰り返しの値が集計?
FROM句のカンマは標準SQLのCross joinとは異なりUNION ALL 演算子
通常のSQL処理システムとは異なり、BigQueryは繰り返しデータの処理を前提として設計。繰り返しレコードの構造を操作するクエリを記述。その方法の1つが、FLATTEN 演算子?
JOINは、INNER、[FULL|RIGHT|LEFT] OUTER、および CROSS JOIN 演算子をサポート、デフォルトINNER
除外できる select + from A OMIT RECORD IF COUNT(payload.pages.page_name) <= 80;
TOP を使用するには、SELECT 句に COUNT(*) を含める
分析関数over()とwindowで計算ができる?(標準SQLと同様?)
functionを作って使える(標準SQLと同様?)
JSON等のネストをフラット化
■DDL
データ定義言語ステートメントの使用 | BigQuery | Google Cloudhttps://www.isoroot.jp/blog/1651/
auto_incrementもdefaultもprimary keyもindexもshow create tableないのでは?
CREATE TABLE IF NOT EXISTS bangboo_data.x_xxx (
`no` INT64 NOT NULL,
`user_no` INT64 NOT NULL,
`name` STRING,
`date` DATETIME,
)
同じスキーマで作ることもできる
CREATE TABLE ore_ds.test003
LIKE prj.ds.test001
PARTITION BY _PATITIONDATE
■bqコマンドはコンソールで実行できる
ブラウザで該当プロジェクトに入りコンソールボタン、下記ではスキーマをJSONで取得できる
bq show --schema --format=prettyjson myProject:myDataset.tbl001
bq ls -n 3000 dataset_aho (データセット内のリスト3000件、デフォ50件?)
bq cp --force prj:ds.tbl prj:ds.tbl2
上書きコピー(削除しコピー)コンソールだと同名コピーや下記ができない
bq cp ds.tbl1,ds.tbl2 ds.newtbl
2つのテーブルをnewtable にまとめコピー
bq cp -a ds.tbl2 ds.tbl1
tbl2をtbl1に追加コピー --append_table でも同じ
bq load (csvとかgcsのファイルを読み込む)
bq extract (gcsに抽出)
■データアップロード時のスキーマ指定
自動検出はFirestore、Datastore、Avro、Parquet、ORCだけ?ほぼ手動のutf-8のcsvかjsonlかを使う形
コンソールで手動スキーマ指定可(jsonスキーマを張付ける)、modeは省略可でデフォはnullable、
JSONスキーマファイルupはaqコマンドのみ可、ローカルからup時のコマンドとスキーマ例↓
bq load --source_format=CSV mydataset.mytable ./myfile.csv ./myschema.json
[
{
"description": "quarter",
"mode": "REQUIRED",
"name": "qtr",
"type": "STRING"
},
{
"description": "total sales",
"mode": "NULLABLE",
"name": "sales",
"type": "FLOAT"
}
]
COUNT DISTINCTだが、BigQueryでは概算値が返ってくる??。正確な値が必要な場合は、GROUP EACH BYとCOUNT(*)を組み合わせる
///Saved query
プロジェクトに対して保存をして使いまわす等ができる
URLでクエリを共有できる
///Federated Query
スプレッドシートやGCSの外部ソースをBigQueryで
範囲の書き方:シート1!A1:B100
Auto detectにするとHeader skipを1にして1行目をカラム名として使うといい
注意)
シートで構成を変えると滅茶苦茶になる
空欄のセルはnullになる
使う人はBQへもスプレッドシートへも両方権限が必要
///パラメータ(変数)を使う
--parameter=min_count:INT64:250
SELECT word FROM `prj.ds.t` WHERE AND count >= @min_count
パラメータ化されたクエリの実行 | BigQuery | Google Cloudこういう感じでも使えるのでは
WITH params AS (
SELECT @sheetInput AS p
),
tmp_pre_processed_src AS (
SELECT * FROM src
)
SELECT * FROM tmp_pre_processed_src
,params
WHERE
tmp_pre_processed_src.a = p
///*を受ける_TABLE_SUFFIXを使う(複数テーブルだとunion allになる)
SELECT year FROM `bigquery-public-data.ds.gsod19*`
WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN '29' and '35'
ワイルドカード テーブルを使用した複数テーブルに対するクエリ | BigQuery | Google Cloud BTWで絞らないと全結合で課金が厳しいかも
※ワイルドカード注意
dataset.product_*と書くとdataset.product_20190425だけでなくdataset.product_special_20190425にもヒットしてしまう
betweenは小さいから大きいで、パーティションのないシャーディングテーブル日付きつきテーブルでも行ける(From句のテーブルに動的な名前を使うにはこれか、EXE IMEDIATEくらいか?)
SELECT year FROM `bigquery-public-data.ds.gsod20*`
where _TABLE_FUFFIX between format_date('%y%m%d', date_sub(current_date("Asia/Tokyo"), interval 3 day))
and format_date('%y%m%d', current_date("Asia/Tokyo"))
///時間のパラメータを使う
select * from mytable_{run_time-1h|"%Y%m%d"}
実行時間run_time(UTC)から1時間引いた日→mytable_20180214
クエリのスケジューリング | BigQuery | Google Cloud///動的にテーブル名を指定してcreate table
パラメータや変数や_TABLE_FUFFIXだけでは難しい。変数はテーブル名とは解釈されない、_table_fuffixはselect分のfrom句に入れwhere句で内容を指定するがcreate分は無理、execute immediateを用いる
DECLARE t STRING;
SET t = (SELECT CONCAT('x_emp_at', FORMAT_DATE("%Y%m%d", DATE_ADD(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 DAY))));
EXECUTE IMMEDIATE format('CREATE OR REPLACE TABLE `%s` AS SELECT * FROM `prj.bangboo_data.x_employee`', t);
ScheduledQueryでは出力テーブルの指定が可能でテーブル指定例:table001_{run_time-1h|"%Y%m%d"}でOK、なおSQL内にはrun_timeが使用できない
//動的にSQLを作成し実行(組織レベルのメタデータを取得
DECLARE all_meta STRING;
SET all meta = (
with projects AS(
SELECT DISTINCT project_id from region-us.INFORMATION_SCHEMA.TABLE_STORAGE_BY_ORGANIZATION
WHERE project_id NOT IN ('対象外プロジェクト)
),
sql AS(
SELECT
CONCAT('select from`', project_id, "`.`region-us`.INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA_OPTIONS", "\nUNION DISTINCT\n') AS s FROM projects
),
concat_sql AS(
SELECT REGEXP REPLACE(STRING AGG(s, ''), '(UNIION DISTINCT+)$', '') AS concat_s
FROM sql
)
SELECT SUBSTR(concat_s, 1, LENGTH(concat_s) - 16) AS all_meta
FROM concat_sql
);
--Scheduled query化ならcreate文にする
--EXECUTE IMMEDIATE format('CREATE OR REPLACE TABLE `bq_us_all_dataset` AS %s', all meta);
EXECUTE IMMEDIATE format('%s', all_meta);
///既存のテーブルをコピー(CREATE OR REPLACE TABLEもあり)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS bangboo_data.x_employee_copy (
`no` INT64 NOT NULL,
`name` STRING,
) as
select * from `prj.bangboo_data.x_employee`
データ定義言語ステートメントの使用 | BigQuery | Google Cloud///timestampとdatetime
datetime型カラムにはCURRENT_DATETIME()、timestamp型カラムにはCURRENT_TIMESTAMP()を使う
timestampはUTC、datetimeはローカル的で地域指定ができる
直近3分
SELECT * FROM `aaa.ds.tbl111`
WHERE `date` > DATETIME_SUB(CURRENT_DATETIME(), INTERVAL 3 MINUTE)
//stringとdate
func_approved_routine_a('2021-10-31') 引数がstring型
func_approved_routine_a("2021-10-31") 引数がdate型
///日付のキャスト
CAST(date AS STRING)
TIMESTAMP(DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 month))
BigQueryのStandardSQLで日付(date, datetime, timestamp)を変換する方法 - 寝ても覚めてもこんぴうた (hatenablog.com)Bigqueryの日時に関係する関数全部試してみた ①Date編 - Qiita///timeで入っているものを日でサマるSQL
select
count(table_id),
sum(size_bytes),
date(record_time) as record_day
from bq_metadata
where record_time > TIMESTAMP(DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 3 month))
group by record_day
order by record_day DESC
///有効期限 table expiration
データセットに対して何日間かにするか設定できる
テーブルに対し特定の日付を設定できる
何が起こる?>データセット自体は残るが中のテーブルが無くなる
///パーティション
パーティション分割テーブルの概要 | BigQuery | Google CloudBigQueryのStandardSQLで日付(date, datetime, timestamp)を変換する方法 - 寝ても覚めてもこんぴうた (hatenablog.com)パーティション分割テーブルは2種類:パーティショニングとシャーディング
●シャーディングテーブル
カラムの増減OK、スキーマとメタデータを持ち権限検証され オーバヘッド有り、ワイルドカード誤操作しやすい→保存向き
●パーティションテーブル
クエリが早い、カラムの増減に対応できない、上限4000位→利用向き
●シャーディングテーブルにパーティション設定
各シャーディングtblでパーティションを持たせる、特殊用途で通常どちらかで
TIMESTAMP 列とDATETIME列では、パーティションを時間単位、日単位、月単位、年単 位のいずれで
SQで自動的にtimestampでDAYになる、SQ実行頻度から自動設定される?
ワイルドカード誤操作 *だと_fuyou_20240401等の想定外も含むため_202*にする等の考 慮が必要
シャーディングの作り方、yyyymmではダメだった、create文でテーブル名にyyyymmddを 付ける あるいはSQのテーブル名に_{run_time-2h["%Y%m%d"}等
シャーディングはテーブルごとに権限を付与が必要で日付別なら実質無理でデータセットで権限管理が必要
クラスタリング も同時に考慮したい
事前にソートし、まとまりを作っておく仕組み。
インデックスのようにカーディナリティが高いカラムを指定してあげると列指向のため全スキャンしなくて良くなる。圧縮率も上がり 保存費用も削減できる。
WHERE で指定あるいは GROUP BY される複数列をクラスタ化列として指定するが、指定の順番が重要。
まずパーティションが考慮され、次に最初にクラスタ指定した列で行がソートされ、次にその中で2番めに指定した列でソート、次に3番目...となる
CREATE TABLE ds.tbl_cls (purchase_dt DATE, prod_id STRING, prod_name STRING)
PARTITION BY purchase dt
CLUSTER BY prod_id
1)パーティショニング
BigQueryでパーティション分割テーブルを作成する - goodbyegangsterのブログ (hatenablog.com) を見よ
パーティショニングは事前に作っておくこと
上限が4000のため最大日単位で11年、時間単位で5か月くらいでpartition_expiration_daysも指定しておく事
CREATE TABLE sample.n225 (
trading_day DATE NOT NULL OPTIONS(description="取引日"),
closing_quotation NUMERIC NOT NULL OPTIONS(description="終値"),
opening_quotation NUMERIC NOT NULL OPTIONS(description="始値"),
high NUMERIC NOT NULL OPTIONS(description="高値"),
low NUMERIC NOT NULL OPTIONS(description="低値")
)
PARTITION BY
DATE_TRUNC(trading_day, MONTH)
OPTIONS (
partition_expiration_days=1825,
require_partition_filter=true,
friendly_name="日経225時系列データ",
description="月別パーティションされた、201901から202107までの日経225時系列データ",
labels=[("environ", "dev")]
)
クエリはpartitioned byのヤツで絞れば良い
select * from aaa_history wehre
#ParticionIDで絞る(つーかpartitioned byのヤツで日付をキャストしてUTCをJST日付に
date(rec_time) = date(datetime_add(datetime "2000-10-10 00:00:00" interval -9 hour))
AND
#実際の時間で絞る、パーティションが日付区切りなので時間検索だけなら全件検索になる
datetime(rec_time) between datetime_add(datetime "2000-10-10 00:00:00" interval -9 hour)
and datetime_add(datetime "2000-10-10 00:59:59" interval -9 hour)
2)シャーディング
シャーディングは_TABLE_SUFFIXを使ったり、テーブル名にハードコーディングする。
日付のキャスト select * from `task_*` where _TABLE_SUFFIX = REPLACE(CAST(date AS STRING), '-', '')
DROP TABLE `task_*`のようにワイルドカードは削除時は使えない
大量削除は下記のようにbq cmdリストを作りBashで。(Terminal貼りつけでも可)
シャーディングはデータセット別にしてデータセットごと消すようにしたいが
Delete BigQuery tables with wildcard - Stack Overflowselect concat("bq rm --project_id prj -f -t ",table_schema,".", table_name, ";" )
from INSERT_YOUR_DATASET_NAME.INFORMATION_SCHEMA.TABLES
where table_name like "INSERT_YOUR_TABLE_NAME_%"
order by table_name desc
シャーディングテーブルのビュー化 (Authorized view/routineの設定も必要)
■ その1(_TABLE_SUFFIXカラムが付くが、全期間取得できる)
CREATE OR REPLACE VIEW ds.tablen_snapshot_all AS
SELECT *,
_TABLE_SUFFIX AS table_suffix
FROM gcp-prj-name.ds.tablen_snapshot_**
WHERE_TABLE_SUFFIX BETWEEN '20200101' AND FORMAT_DATE('%Y%m%d',
CURRENT_DATE())
↓下記のように使用する
SELECT FROM `ds.tablen_snapshot_all
WHERE table_suffix BETWEEN '20250530' AND '20250601'
あるいは
SELECT FROM tablen_snapshot_all
WHERE table suffix = '20250601'
■その2 (テーブル関数のため単一日付のみ取得)
CREATE OR REPLACE TABLE FUNCTION ds.fn_tablen_snapshot_by_date(date_str STRING)
AS
SELECT
FROM gcp-prj-name.ds.tablen_snapshot_**
WHERE TABLE_SUFFIX = date_str;
↓下記のように使用する
SELECT FROM `ds.fn_tablen_snapshot_by_date("20250601");
削除されたテーブルは7日以内なら復元することも可能
テーブルの管理 | BigQuery | Google CloudBQタイムトラベルで2-7日前のデータを見れる
タイムトラベルを使用した履歴データへのアクセス | BigQuery | Google Cloud ///UNNEST
UNNESTを知らないとBigQueryを使えない? | 4番は司令塔 (pep4.net)ARRAY を一組の行にフラット化するには、UNNEST 演算子を使用
SELECT id, title FROM games, UNNEST(titles) AS title
| id | titles |
| 1 | [skyrim, fortnite] |
| 2 | [atvvsmx, mario] |
↓フラット化
| id | title |
| 1 | skyrim |
| 1 | fortnite |
| 2 | atvvsmx |
| 2 | mario |
ただしUNNESTで指定したカラムが空の配列やNULLの場合、該当行は無くなってしまうので注意
id=3 titles=[]やid=4 titles=NULLの時はid=3,4は引っ張れないということ
select * from unnest(['aaa', 'bbb']) as baka -> rowとして2行出る
select ['aaa', 'bbb'] as baka -> 1行目に配列として全て含まれ出る
sql - How to query multiple nested fields in Bigquery? - Stack OverflowUnnestでもflattenができず空欄ができる場合、結局left join
空を含むカラムはSelectに残し、repeatedのカラムはleft joinでくっつける
VariantsをunnestしてるがPricesもrepeatedなのでleft joinのものを出している
repeatedもarrayと同じらしいが、、、cross joinやarray_to_stringもやったが駄目だった
なおrepeated以外はunnestが効かない
それでも駄目ならselect句の指定方法やwhere句で絞ると空欄が抜けたよ
select Productid,Variants.SKU,Variants.Size
,Prices.Currency,Prices.Country
from `ga-export-0000.feed.feed_dev`
,UNNEST (Variants) AS Variants
LEFT JOIN UNNEST(Variants.Prices) as Prices
///ARRAY型とSTRUCT型
Arrayは上のUnnestを参照。
Structは構造体型。順序付きで親子の構造を持つ。各フィールドはデータ型(必須)とフィールド名(オプション)を持つ。
array型 unnestできる、[]なのでarray_length()で数が取れる
struct型 unnestできる、ネストを含みスキーマでrecord型と表記される、struct型の子へは.ドットで指定す
stringでJSONはjson_extractを使う
配列との絡みでjson_query_arrayを使う、2段階くらいは関数で対処できるがそれ以上はwith句がいい
BigQueryでの複雑なJSON文字列の扱い方と注意点 - Qiita JSON functions | BigQuery | Google CloudCREATE TABLE IF NOT EXISTS `bangboo-prj.ds.x_list` (
`record_time` TIMESTAMP,
`name` ARRAY
)
INSERT INTO `bangboo-prj.ds.x_list` (`record_time`,`name`) VALUES (CURRENT_TIMESTAMP(),['a','b'])
struct型(record型)は子や孫でヒットすれば親を含めて表示されてしまう
見やすくするため*ではなく、カラムを特定すると空欄が表示されなくなり
親が出なくなり理解しやすくなる(必ずカラム指定したい)
Array=String Repeatedつまりリスト(配列)に値を入れる書式(下記で2つしか入らない)
insert into aaa (aaa) value ("['aaa','bbb']") value has STRING
insert into aaa (aaa) value (`['aaa','bbb']`) Unrecognized name: `['aaa','bbb']`
insert into aaa (aaa) value (['aaa','bbb']) OK
insert into aaa (aaa) value ('["aaa","bbb"]') value has STRING
insert into aaa (aaa) value (`["aaa","bbb"]`) Unecognized name
insert into aaa (aaa) value (["aaa","bbb"]) OK
insert into aaa (aaa) value ([`aaa`,`bbb`]) Unrecognized name
insert into aaa (aaa) value ([aaa,bbb]) Unrecognized name: aaa
insert into aaa (aaa) value ([123,456]) Value has type ARRAY
例)権限が変わっていないかの確認する等
降順で最新の日付のアイテムを見る、そして最終ページの古い日付のアイテムを見る
そしてそれらを比較する
select record_time, name, asset_type, m, b.role
from cai_iam_policy_history
,unnest(iam_policy.bindings) b
,unnest(b.members) m
where record_time between timestamp('2021-05-01') and timestamp('2021-06-30')
and b.role in ("roles/bigquery.dataViewer", "roles/bigquery/jobUser")
and m like '%ketsu@bangboo.com%'
and ancestor_path like '%ketsuproject%'
order by record_time desc
SQL解説)struct型が沢山入っていても全部unnestしfromに入れればいい
from a, unnest(iam_policy.bindings) b, unnest(b.members) m
unnest(iam_policy)はできないので2階層目から
一つ階層上ではunnest時に別名を付けて下の階層はその別名でunnest
struct型の子へは.ドットで指定すればいい、フラットでなくてもbでも取得ができる
↑
通常SQLは「表.カラム」だが「親カラム.子カラム」なので、出元がどこかテーブルを探すかスキーマ内を探すかで迷う
///json_extract, json_extract_scalar
2番目の引数はパス
BigQueryでの複雑なJSON文字列の扱い方と注意点 - Qiita標準 SQL の JSON 関数 | BigQuery | Google Cloudwith t as (
SELECT unco_data AS col_1 FROM `kuso`
WHERE date = "2021-08-04"
)
SELECT
json_extract(col_1, '$.color') as unco_color,
json_extract(col_1, '$.temperature') as temperature,
json_extract(col_1, '$.fart.times[0].stink') as first_stink,
FROM t
)
PIVOT(
MAX( IF (active IS NOT NULL, 1, 0))
FOR user IN ("a", "b")
)
↓
tool a b
------------
axe 1 0
sword 0 1
※参考にピボットテーブル
集計して行を列に変換、生ログをある単位でまとめる
生ログが「日 店 金額」の場合
↓
ピボットで「日 金額 (店1 店2 店3)」にする等で、各項目を行と列と値に配置し直す
BigQueryでPreviewになったPIVOTとUNPIVOTを試す | DevelopersIO (classmethod.jp)PIVOTの中は定数でないとだめだが、
Execute Immediate なら動的にイケる、
がGoogleSheetのConnectedSheetではサポートされておらず無理という罠
///縦持ち横持ち
pivotは集計関数を用いる、単純の入れ替えならSQLならこちら
[SQL]データの縦持ち、横持ちを入れ替える | DevelopersIO (classmethod.jp)///新旧の差分
比較したいデータの共通してい部分で外部結合をしてnull部分を探す
WITH
old_e AS (
SELECT * FROM status WHERE user IN ('a@old.com')
),
new_e AS (
SELECT * FROM status WHERE user IN ('a@new.com')
)
SELECT * FROM old_e o
FULL OUTER JOIN new_e n ON o.id = n.id AND o.date = n.date
WHERE o.id is null OR n.id is null
ORDER BY o.id, o.date
unionにexcept distinctをSQLを付けると差分になる
https://qiita.com/tatsuhiko_kawabe/items/2537c562c6d99f83e37b
SELECT * FROM item.item_table
EXCEPT DISTINCT
SELECT * FROM item.item_table WHERE user_id = 'A'
1つ目の結果から2つ目を引いたものを出す
///REGEXP_REPLACE 正規表現で文字を削除
WITH markdown AS
(SELECT "# Heading" as heading
UNION ALL
SELECT "# Another Heading" as heading)
SELECT
REGEXP_REPLACE(heading, r"^# He", "") AS html
FROM markdown;
標準 SQL の文字列関数 | BigQuery | Google Cloud///スラッシュで分割するとarrayになるのでオフセットで取得
select SPLIT(path, "/")[OFFSET(3)] from www
スラッシュの最後を取る
ARRAY_REVERSE(SPLIT(aaa, "/"))[SAFE_OFFSET(0)]
///Job kill
CALL BQ.JOBS.CANCEL('job_id')
CALL BQ.JOBS.CANCEL('project_id.job_id')
job idでエラー詳細を確認
bq show -j
bq show --project_id bangboo_sandbox --format json -j bqjobidxxxxxxxxxx | jp .
job idはコンソールのBQのジョブ詳細やスクリプトキックならロギングから見つけてもいい
クエリならjob/query historyでわかるがbq cmdでもエラーが返る
bq query --nouse_legacy_sql 'select ketsu from `prj`.oshi.ri'
unrecognized name: 'kusofuke@ketsu.com' at [1:149]
select * from prj.`region-us`.INFORMATION_SCHEMA.JOBS_BY_PROJECT
where job_id ="aaaaa" and creation_time > "2022-01-01"
ジョブIDの取得
SELECT
project_id,
job_id,
user_email,
creation_time,
start_time,
--query,
total_slot_ms
FROM `region-us`.INFORMATION_SCHEMA.JOBS_BY_PROJECT
--`region-us`.INFORMATION_SCHEMA.JOBS_BY_USER
--`region-us`.INFORMATION_SCHEMA.JOBS_BY_FOLDER
--`region-us`.INFORMATION_SCHEMA.JOBS_BY_ORGANIZATION
WHERE state != "DONE"
--state = "RUNNING"
--state = "PENDING"
AND user_email = 'my@email.com'
AND project_id = 'paa'
AND start_time < TIMESTAMP_SUB(CURRENT_TIMESTAMP(), INTERVAL 3 MINUTE)
AND total_slot_ms > (1000 * 30)
AND PARTITIONDATE BETWEEN '2021-01-01' AND '2021-01-02'
--PARTITIONTIME BETWEEN TIMESTAMP('2021-01-01') AND TIMESTAMP('2021-01-02')
///upsert(アップデートか新規インサート
https://swfz.hatenablog.com/entry/2021/02/08/195024
MERGE aaa target USING tmptbl src
ON target.time = src.time
WHEN MATCHED AND src.satus = 'rejected' THEN
DELETE
WHEN MATCHED THEN
UPDATE SET ...
WHEN NOT MATCHED THEN
INSERT ROW
///window関数
集約関数(GROUP BY)だと個別データは出力されず集計データだけでるが
window関数だと集計データが個別データにouter joinされた形で出力される
SELECT
deptname,
id,
salary,
AVG(salary) OVER (PARTITION BY deptname)
FROM emp;
deptname | id | salary | avg_salary
-----------+-------+--------+-------------
dev | 11 | 5200 | 5020
dev | 7 | 4200 | 5020
dev | 9 | 4500 | 5020
dev | 8 | 6000 | 5020
dev | 10 | 5200 | 5020
hr | 5 | 3500 | 3700
hr | 2 | 3900 | 3700
sales | 3 | 4800 | 4866
sales | 1 | 5000 | 4866
sales | 4 | 4800 | 4866
deptnameでグループしそのsalaryの集計のAVGが出ている
下のようにover()が空でも良い、4900は大体
SELECT
deptname,
id,
salary,
AVG(salary) OVER () AS avg
FROM emp;
deptname | id | salary | avg
-----------+-------+--------+-------------
dev | 11 | 5200 | 4900
dev | 7 | 4200 | 4900
dev | 9 | 4500 | 4900
dev | 8 | 6000 | 4900
dev | 10 | 5200 | 4900
hr | 5 | 3500 | 4900
hr | 2 | 3900 | 4900
sales | 3 | 4800 | 4900
sales | 1 | 5000 | 4900
sales | 4 | 4800 | 4900
関数としては集計関数がそのまま使えるようだ
OVERはwindow関数を使う宣言、OVERの後にどのようにwindowを作るのかを定義
PARTITIONでwindowでつまりどの範囲でグループを作るか指定
AVG(salary) OVER (PARTITION BY deptname, sub_deptname) でサブデプト単位での平均となる
///誰が実行しているかをセッションユーザで出す
標準 SQL のセキュリティ関数 | BigQuery | Google CloudSELECT SESSION_USER() as user;
+----------------------+
| user |
+----------------------+
| jdoe@example.com |
+----------------------+
///エラーハンドリング
BQのクエリ内の条件によりerror()でエラーが吐ける
///プログラムで使う
from google.cloud import bigquery
client = bigquery.Client()
QUERY = ('SELECT name FROM `bigquery-public-data.usa_names.usa_1910_2013`')
query_job = client.query(QUERY)
rows = query_job.result()
for row in rows:
print(row.name)
///Pythonも含めトランザクション
/// BANGBOO BLOG /// - GCP script■saturationの場合、詰まっている、サチっている
対象にクエリを発行 select 1
同プロジェクトの他のテーブルにクエリを発行 select 1
別プロジェクトから対象にクエリを発行 select 1
reservationsのoverviewを見る
対象のSQLを発行
別のプロジェクトで同SQLを発行
時間を比べる
Google側の問題と思われるときはGoogleのサポートへGo
Google Could Status
Google Cloud Status DashboardINFORMATION_SCHEMA < Audit log で調査
メタデータ(データに対するデータ)
システムメタデータ(作成更新日時、サイズ、誰いつ参照
ビジネスメタデータ(オーナ、更新頻度、カラムの意味
select * from prj.ds.INFORMATON_SCHEMA.TABLES
select * from prj.ds.INFORMATON_SCHEMA.PARTITIONS
longterm storageでサイズが100000b以上で、更新日が1か月以上とか出せる
select * from prj.ds.INFORMATON_SCHEMA.COLUMNS where column_name like '%kuso%'
select * from prj.ds.INFORMATON_SCHEMA.VIEWS where view_definition like '%kuso_table%'
view_definitionはSQL文が入っている
select * from prj.ds.INFORMATON_SCHEMA.JOBS_BY_(USER / PROJECT / ORGANIZATION)
誰アクセス/誰作った/何Job等も分かる、180日しか出せないが
roles.bigquery.resourceViewerが必要
カラム例:user_email、query、referenced_tables
Auditlogは プロジェクト間で使用されるBQでも情報が取れる
info_schemaのjobs_byとほぼ同じ内容が取れるがよりリッチ
利用ユーザ数、旧データを見ている人、権限変更操作ログ等
SELECT `b-sandbox`.test_ds.count_row(1); で実行できる
UDFやテーブル関数のルーティンを承認しておくと誰からでも使える(ビューと違い権限管理できずセキュリティがズブズブになると思われ)
target_prj.trg_dsに受け入れる関数を共有指定する形
UDFは戻り値がある、テーブル関数は副問い合わせとして使う形か
///ScheduledQueryの実行者
コンソールの場合:コンソール操作者
Terraformの場合:Terraform実行者
bqコマンドの場合:任意に設定ができる
サービスアカウントをbqコマンドでSQ実行者として登録する場合、通常は問題がないがスプレッドシートを使用するなら@プロジェクト名.iam.gserviceaccount.com等でアクセス権が必要なため、会社のポリシーによってはうまく行かない。batch@unco.comのような共通メールを作成し使用したい。(GWS側でOUを使いTrusted ruleによりSAにGoogleDriveへアクセス許可すると問題回避できるが:OUをつくりそのOU内で専用共有ドライブを作成し設定する)
サービスアカウントにScheduleQueryを実行させる設定に必要な権限
https://cloud.google.com/bigquery/docs/scheduling-queries?hl=ja
設定操作者
BQ job user(クエリ作成ができない)
BQ transfers.get/update
BQ data viewer/editor
iam ServiceAccountUser(対象SA、PRJレベルでも良いが広くimpersonateできてしまう)
→対象SAのみならlistも含むがlistが不足しているとされ serviceAccountViewerをPRJレベル付与も必要
保存先DSへBQ admin等へのsetiam系が2026/3から必要
サービスアカウント
BQ job user
BQ data viewer/editor
※BQ transferは不要だった
Scheduled queryからの保存先
コンソールだと同じプロジェクト内だが、create文を自由記載ならどこでもOK
job userは同じプロジェクトの権限が必要
設定者一覧を出したい場合
bq --format=json --project_id=bangboo-oketsu ls --transfer_config --transfer_location=us | jq.[].name
bq --format=json show --transfer_config project/1111111/locations/us/tranferConfigs/111111 | jq .ownerInfo.email
■SQLはカラム数の増加数で構成考える?
left outer joinはカラム数がカラム数の合計から共通のjoin onのカラム数を引いた数(行数はleftに同じ)
full outer join はカラム数がカラム数の合計から共通のjoin onのカラム数を引いた数(行数はleftの要素数にrightの要素数を合計したもの)
unionは重複を除外し表を足し合わせるため行数が両表の合計行数(カラム数は合致必要でカラム数は変わらない)
unian allは重複を除外せず表を足し合わせるため行数が両表の合計行数(カラム数は合致必要でカラム数は変わらない)
cross joinはカラム数が両表のカラム数の合計、行数は両表の行数の掛け算
再帰的にSQL処理はcross joinし条件を付けるか?
■課金
クエリ課金:使用しているプロジェクトで課金される、データの置き場所ではない
定額フラット:$2000/100slot/m(全プロジェクトでスロットを共有)、オンデマンド:$5/T=2Gスキャンで1円位
flat rateでもflex slotsとして時間帯によりスロットを増やす等ができる
Editionsに変更になった:組織に5プロジェクト等しかreservationを置けない、その中で限りなく設定ができる
課金を減らすには:カラムを減らす、パーティショニング
プレビューを活用:しかしビューだとプレビュー機能はない。列が501列以上あったら501列以降はプレビュー出ない
データ保管課金:データ量
$1/50G/m
active storageからlong term storageへの移行は自動(90日変更がない、50%off)
6,000スロットを使うBigQueryのリソース配分最適化への挑戦 (plaid.co.jp)■定額制Editions
スキャンサイズが大きくてコンピューティングが少ないならリザベーション (Editions)が向いている、スキャンサイズが小さくてコンピューティングが多いならオンデマンドが向いている
スロット消費量=データ量とコンピューティング
1)データ量: Read量/スキャン量 (スキャン量が多くても単純クエリならスロット消費が少なく単純な比例ではない)
2)コンピューティング負荷: CPU/メモリ消費 (結合/集合/フィルタ/ソート/大量JOIN/複雑なウィンドウ関数等で重いクエリ)
■オンデマンド
必要なクエリ以外は別の定額制のプロジェクトで実行するよう変更
オンデマンドはスキャンしたデータ量で料金が決まる
実行しているクエリのスキャン量で料金を見積もる
パーティション、クラスタリングでスキャン量を減らす
SELECTはNG。必ず必要な列だけを明示する。
スキャン量のモニタリングとアラート設定を実施する。
同じクエリならキャッシュが利くため定額のエディションが有利(24h)
ソースの更新等でキャッシュが無効になるよ
■権限
事前定義ロールと権限 | BigQuery | Google Cloudjob user:select文クエリ実行だけでもジョブでjob userとdata viewerが要る(data viewerだけでは不足)
課金プロジェクトでjob userを持ち、参照先プロジェクトでdata viewerを持つという権限構成だから
例えばjob userがなくdata ownerだけの場合はデータセットやテーブルやビューの削除作成ができるが、データロードやselect文発行はできない
IAMかデータセット/tblに必要な権限を付与する
data editorでも自分で作成したものは自分がOwnerになり削除や変更権限がある
meta data viewerならDSとテーブル一覧、テーブルのスキーマや容量等の情報が見れデータは見れない
これを広く付けておくとデータ管理が楽
■サービスアカウントに対するBQ job user
コンソールであれば画面左上の請求先プロジェクトで切り替えができるが
スクリプトであればgcloud auth login時に切り替える
gceならインスタンスにSA設定するが
請求先プロジェクトのデフォルトはインスタンスの置いている/SAが作成されたPrj
※同プロジェクトからしか選択ができない
コード上で切り替えができる
bq --project_id=xxx query 'select count(*) from ds.tbl'
$ python
>>> import sys
>>> sys.path
でパス一覧が出るので探すと分かる >>> exit()でpythonコマンド終了
例えば Cloud functionsなら requrements.txtに google-api-python-client==3.3.2と記載し
PyPI · The Python Package Index でバージョンを探す
コードに from google.cloud import bigqueryと宣言する
requirementがpipインスコ
import フォルダ.ファイル名
from フォルダ.ファイル名 import *
上下同じだが、fromは一部を指定し直接使うという意、*は非推奨
つまり
import hello なら下記とする必要があるが
print(hello.hello)
from hello import hello なら省略ができ下記で良い
print(hello)
from フォルダ名 の場合
そのフォルダ名の中に __init__.pyがあれば其れ
from .xxx import aaa の.の意味は?
mainに対するモジュールから見て相対で隣
モジュール検索パスを出す
from pprint import pprint
import sys
pprint(sys.path)
■pipインスコ
PyPIでサードパーティライブラリを管理していてインスコ可
setup.pyが含まれたローカルディレクトリも指定しインスコ可
eオプションで編集可能な状態でインスコ
--userで~/.local下の管理権限不要なユーザディレクトリ以下でシステムが汚れない
--userなしで/usr下にインスコ
pip install --user -e unko
pip3 install pipenv
pyenv install --list インストールできるもの
pyenv install 3.8.8 指定verをインスコ
pyenv global 3.8.8 デフォルトに指定
.python-versionファイルをGITに載せ管理したい?
pipenvはPipfileとPipfile.lockを利用しpipでrequrements.txtを用いるよりも強力
PipfileとPipfile.lockとrequirementsをGITに載せ管理したい?
pipenv --python 3.8.8 など最初にpyバージョンをpipfileに記載
pipenv install "google-cloud-tasks==1.5.0" バージョン無しでも有りでも入れられる
Pipfileを書き換える方法
[packages]
google-cloud-tasks = "==1.5.0"
protobuf = "*"
そして下記cmdでインスコ
pipenv install PipefileからインストールしPipefile.lockを更新
pipenv sync Pipfile.lockの最新を取得し環境更新(Pipefileは使わない)
pipenv shell 仮想環境を起動
pipenv run python main.py
他に
pipenv uninstall google-cloud-tasks アンインスコ
Pipfile, Pipfile.lockがあれば pip syncでOKだがrequirements.txtも使える
pipenv lock -r > requirements.txt 生成
pipenv install -r requirements.txt
pipenvのバージョンが古いと依存関係、Ver整合性で問題が起きやすい
pipenv --version
pip install pipenv
pipenv update
pipenv upgrade <パケ>でやり直す
■assertでテスト
assert文は組み込み定数__debug__がTrueの時のみ実行されます
実行コマンドにオプションに-Oをつけると__debug__がFalseになりassert文が無効に
def func_so(a, b):
c = a * b
return
def test():
assert(func_so(1,2) == 2)
if __name__ == "__main__":
test()
main()
■テスト駆動
PyTest を LLMに書いてもらいたい。下記のようなプロンプトで準備できるのでは?
https://aaaa にアクセスし名前欄にaaaと入力すると名前欄に英数が入っていますとエラーが出る
■PyTest
assert
成立すべき式(Trueになるべき式) をassert文で記述
テストの準備と後処理
@pytest.fixtureデコレータをつける
実行(ディレクトリのtest、testファイル、test 関数が対象)
pytest
テストカバレッジを確認:tests/ディレクトリ内の全テストを実行し現在のディレクトリ内のコードについてどれだけテストでカバーされているかを測定
pytest -covs=. tests/
■test app.pyでエラー表示を拾ってテスト
import pytest
from app import app
@pytest.fixture
def client():
app.config['TESTING'] = True
with app.test_client() as client:
yield client
def test_valid_input(client):
response = client.post(
'/',
data={'name': 'TestUser', 'email': 'Test@example.com'},
follow_redirects=True
)
assert b'OKでっせ' in response.data
def test_invalid_name(client):
response = client.post(
'/',
data={'name': 'ThisNameIsTooLong', 'email': 'test@example.com'},
follow_redirects=True
)
assert b'name At most 10 characters long' in response.data
def test_invalid_email(client):
response = client.post(
'/',
data={'name': 'ValidName', 'email': 'Invalid email'},
follow_redirects=True
)
assert b'emailがinvalid email addressなんだけど' in response.data
■パラメータを複数種類
import pytest
@pytest.mark.parametrize(
"x, y", [
("aaa", "bbb"),
("aaa", "aaa"),
("bbb", "bbb")
]
)
def test_1(x, y):
assert x == y
■fixture: fixture@yieldまでの処理> テスト本体> fixtureのyield後からreturnまでの処理
import pytest
from pathlib import Path
import shutil
def create_file(path):
# 指定されたパスにファイルを作成する関数
path.touch()
# 一時ディレクトリを作成するフィクスチャ
@pytest.fixture()
def create_tmp_dir():
# 一時ディレクトリを作成
tmp_dir = Path("/tmp/test")
if not tmp_dir.exists():
tmp_dir.mkdir()
yield tmp_dir
# 一時ディレクトリを削除
shutil.rmtree(tmp_dir)
def test_create_file(create_tmp_dir):
target_file = create_tmp_dir / "test.txt"
create_file(target_file)
assert target_file.exists()
■個別
import dataclasses
import datetime
pip install pyyaml > import yaml
pip install requests > import requests
Python + VSCode の環境構築 20240604 (zenn.dev)↓本家
/// BANGBOO BLOG /// - PythonおッPythonやるのか?
ファイル拡張子oppython.py デフォUTF-8、全部オブジェクト(list,dict,set等のミュータブルなら参照になる点に注意、必要ならcopy())
#コメント、ドキュメントストリング(三連引用符):"""そのまま表示""" print mymod.__doc__で見れる
変数型不要:p = 500 * num、でもキャストは必要、定数はない
文字繰り返し、キャスト:"文字列" * 4 + str(p) + "Hi\nお元気ですか?\nSee u"
raw文字列でescしない:print(r"インストール先は c:\\code\python\bin です")
正規表現のrも同意 re_result = re.match('hel', r'hellow python, 123, end.' )
if re_result: #None以外という意味で、Noneはいわゆるnull、Pythonにnullはない
文字数:len("東京都")→3
文字列[開始:終了]→→ str = "Flower" print(str[1:4]) → low
文字列 % (値1, 値2, ...)→→ num= "10進数では %d 、16進数では %x " % (num, num)
"xxxx{index:書式指定子}xxxx".format(値)→→ "名は{:<8s}で年は{:>3d}で".format(name, age)
f"xxxx{値:書式指定子}xxxx"→→ f"名は{name:<8s}で年は{age:>3d}で"
0/空の文字列''/値なしはfalse、Noneは? x = None x is None→→true?
//→除算切り捨てし整数、**→べき乗
関数宣言はdef kansu(): で中で宣言する変数はローカル変数
関数外で宣言された変数はグローバル変数でどの関数の中でも扱えるようになる
なお関数内でもglobal henでグローバル変数を宣言できる
Pythonでのグローバル(global)変数の宣言方法 | UX MILK返り値複数はcsvでタプルになる、リストが楽か? return a,b → (a, b) あるいは return [a, b] → [a, b]
def func(a, b):
return a, b
result = func()
result[0]がa、result[1]がb
try/exceptを関数内で設定することも、逆に関数呼び出し時にも使用ができる、else, finally, raiseも使う、エラーが出ても止めたくない場合は try-except Exceptions as e、逆にexceptを入れなければ止まるので安全
try:
get_all_transfer(project_id)
excerpt Exception as e:
print(e)
置換は左辺が要る?要る a = a.replace('x','')
とほほのPython入門 - リスト・タプル・辞書 - とほほのWWW入門 (tohoho-web.com)Pythonの辞書とリストとクラス 複数情報の受け渡し|みはみ|noteリストa=[1,2,3]はmap(), filter(), reduce()等が使える
a=a.append()とかa=a.extend()は値がないんで駄目、単純にappend(b)やextend(b)で左辺不要
取得:a[0]、for v in a:
リストの合体:list_a += list_b
セット型set={1,2,3}は重複や順序や添字の無いリスト、set(list)でキャストし重複を無くせる、ミュータブルは格納できない
取得 for v in a:
tuple→タプルは定数リスト、更新無しならリストより速い a = 1,2,3 a = (1, 2, 3)
取得:a[0]、for num in a:
dict→辞書は連想配列みたいな{a:1,b:2}はitems(), keys(), valus(), iteritems(), get()を使える
Python | 辞書に含まれるすべてのキーと値を取得する (javadrive.jp) 取得:dict_a['key1']、for k in dict_a.keys(): for v in dict_a.values(): for k, v in dict_a.items():
dictの合体:dict_a.update(dict_b)
クラス→例えば●●クラスを宣言しsampleインスタンスを生成し、getter/setterで変数に入れて置く
取得:sample.key
BigQuery→別名を付ければ名前で取得できるが、インデックスでも取得できる(これ何?)
取得:for row in query_job: →row[0], row["t"]
lambdaは無名関数?
str_w = input('何か入力してください-->') #入力させた値を取れるが数字もstr
__iter__()はnext()を持つオブジェクトを返し、next()は次の要素を返し、最後に達するとStopIteration例外を返す?
yield はイテレータを返すジェネレータを定義?
@デコレータは関数を実行する前後に特殊な処理を実行したい場合?
withで終了処理を指定できる、ファイル読込とその後の処理とか
assertや__debug__はテストで機体通りかを確認する?
passは中身の無い関数やクラスを作成しkara.p=1で粋なり属性追加等ができる
execは引数の文字列をPythonとして実行 exec "print 'Hello'"
delはオブジェクトを削除 del x, y, z
継承やオーバーライド class MyClass2(MyClass):
多重継承class MyClassC(MyClassA, MyClassB): で纏めて使えるようになる
class MyClass:
"""A simple example class""" # 三重クォートによるコメント
def __init__(self): # コンストラクタ
self.name = ""
def __del__(self): #インスタンスが消滅する際に呼出でコンストラクタ
print "DEL!"
def __str__(self): #文字列化
return "My name is " + self.name
def getName(self): # getName()メソッド
return self.name
def setName(self, name): # setName()メソッド
self.name = name
class MyClass2(MyClass):
def world(self):
print "World"
class MyClass3(MyClass):
def hello(self): # 親クラスのhello()メソッドをオーバーライド
print "HELLO"
a = MyClass() # クラスのインスタンスを生成
a.setName("Tanaka") # setName()メソッドをコール
print a.getName() # getName()メソッドをコール
print a #=> My name is Tanaka 文字列化
b = MyClass2() #継承
b.hello() #=> Hello
b.world() #=> World
c = MyClass3() #オーバーライド
c.hello() #=> HELLO
super()を使ってオーバーライドする
super()は基底クラスのメソッドを継承した上で処理を拡張
super().__init__(x、y)が使える
if __name__ == "__main__":
モジュール時の勝手実行を抑える
import helloの時hello.py 内部での __name__ は "hello"
python hello.pyのような実行時hello.py の内部の __name__ は "__main__"
from math import pi, radians→mathモジュールから特定のオブジェクト(関数/変数/クラス)をimpo(math.piみたいに書かず省略できる)
import urllib.error→urllibパッケージからerrorモジュールをimpo、パッケージはフォルダ
import numpy as np→別名でしか使えなくなるnp.array()とかで
モジュール=ファイル名.pyでファイルをimpoしている
from {another_file} import {ClassName}
another_file.pyがファイル名
class ClassNameがクラス名
from {パッケージ:ディレクトリ} import {モジュール:ファイル}
ちゅー書き方もできるらしいが、どっち?
impo順:標準ライブラリ>サードパーティライブラリ>ローカルライブラリ(自作のライブラリ)
関数や変数:小文字スネークケース(sample_func)
クラス名、例外、型変数:キャピタルパスカルケース(SampleClass)
定数名:大文字アンダースコア区切り(SAMPLE_CONST)
モジュール名:小文字(samplemodule, sample_module)
パッケージ(フォルダ)名:小文字。アンダースコア非推奨(samplepackage)
インデントは半角スペース4つ
1行半角で79文字以内
トップレベルの関数やクラスは2行開ける
デバッグの方法案
print(type(v)) でどんなメソッドを持っているか等を探る
print(v) をコマンド前後や流れで沢山仕込みでどこでエラーが出ているか探す
print("creds:")
print(creds)
print("type(creds:")
print(type(creds))
print("vars(creds:")
print(vars(creds))
print("creds.keys():")
print(creds.keys())
print("dir(creds):")
print(dir(creds))
print("creds._dict_:")
print(creds.__dict__)
is not subscriptableのエラー 添字不可エラーでリストでないのにリストとして入れようとしている
※参照になりコピーされない、必要ならコピー(値を入れた時点で参照が外れるので実際問題少ない?)
a = []
b = a
b.append(1)
print(a) #[1]
https://qiita.com/ponnhide/items/cda0f3f7ac88262eb31e
https://nishiohirokazu.hatenadiary.org/entry/20120125/1327461670
環境変数を扱う
import os
print(os.environ["HOME"]) ホームディレクトリ、LANGでja_JP.UTF-8とか
os.environ["PHASE"] = "staging" 環境変数に代入できるのは文字列だけ
del os.environ["PHASE"] 削除
コマンドラインの引数を扱う
python3 sys_arg_test.py a 100
dst_prj = sys.argv[1] (aが入っている)
sys.argv (['sys_arg_test.py','a','100']
i = 0
v = "["
for s in list_v:
i += 1
if i > 1:
v += ","
v += "'" + s + "'"
v += "]"
SQL = "insert into aaa (aaa) value ({v})"
※テキスト選択
Shift↑or↓ で行全体
home(+fn)で行頭、end(+fn)で行末移動
【基礎一覧】Pythonの基本文法を全て解説してみた!【初心者】 (suwaru.tokyo)Python基本文法まとめ - QiitaとほほのPython入門 - とほほのWWW入門 (tohoho-web.com)HTMLの中に少し埋め込めず、基本的にプログラムの中にHTMLを埋め込む:CGI(Perl然)
さくらインターネットでPython CGI (mwsoft.jp)WSGI
Python で WSGI (Web Server Gateway Interface) に従ったシンプルな Web サーバで Hello World - QiitaPython用Webサイト用途フレームワーク:Flask(軽量)、Django
WSGI について — Webアプリケーションフレームワークの作り方 in Python (c-bata.link) GCPでどう使うかは不明だがホスティングは↓
ウェブ ホスティング | Google Cloud 静的ウェブサイトのホスティング | Cloud Storage | Google Cloudstr.split() 区切り文字で分割しリスト等に入れる
Pythonで文字列を分割(区切り文字、改行、正規表現、文字数) | note.nkmk.meprint('Sam' in 'I am Sam') # True 任意の文字列を含むか判定: in演算子
Pythonで文字列を検索(〜を含むか判定、位置取得、カウント) | note.nkmk.me==============
ここで動かせるgoogle colaboratory→
Colaboratory へようこそ - Colaboratory (google.com)半角スペース2個で改行
#の数で見出し
*で箇条書き
数字と.で番号を振る、- でリスト
* or - or _ を3つ以上で水平線
[ ]でチェックボックス、[x]でチェック
| td | td | td |でテーブル
**aaa**で太字、*aaa*で斜体
~~aaa~~で打消し線
[タイトル](URL)でリンク
```でコードの挿入、`でインライン挿入
> or >> で引用
[^1]で注釈
\バックスラッシュでマークダウンのエスケープ
==============
宗教論争(事実は同じでも他人の認知は違うので意味なし
if self.flag_ok == 1 and self.mode == '1'
↓一見で分からんなら変数名を工夫してこうやんな
if self.file_verify_completed and self.mode == GRANT_PERMISSION:
マジックナンバーを使わない(数字の方が曖昧性が無い場合も)
STATUS_ERROR = -1
STATUS_SUCCESS = 0
self.status_error = STATUS_SUCCESS
with構文で処理の前後でコンテキストマネジャ__enter__、__exit__が使われる
__enter__メソッドで事前処理
__exit__メソッドで事後処理
with ファイル操作や通信などの開始時の前処理と終了時の後処理など必須となる処理を自動で実行
try/finallyみたいなもの、最初と最後に何かしてくれる
class a(object):
def_enter_(self):
print 'sss'
return 'sss111'
def_exit__(self, type, value, traceback):
print 'ok'
return False
with a() as s:
print s
sss
sss111
ok
初期値をエラー値にし、業務判定エラーでステータスを設定したらreturnで抜ける
def exFunction(self):
self.status_error = STATUS_ERROR
try:
if XX = AAA:
self.status_error = STATUS_XX_ERROR
retrun
self.status_error = STATUS_SUCCESS
retrun
except:
~エラー処理、ステータスは変更しない
エラーメッセのハードコーディングを避ける方法(ハードが場所と内容が分かり易いかも)
MSG_ERROR_OLD_EMAIL = "Error: 旧メール%sです\n"
e_message_list.append(MSG_ERROR_OLD_EMAIL % (old_email))
self.error_message = '\n'.join(e_message_list)
ケチって分厚い本1冊にしたが全然進まぬ、薄い奴星e、?チッPython、誰がJSONじゃ~い、チェーンソー魔わすっぞ
続編、、モジュールとかmportとか、
/// BANGBOO BLOG /// - Python Python
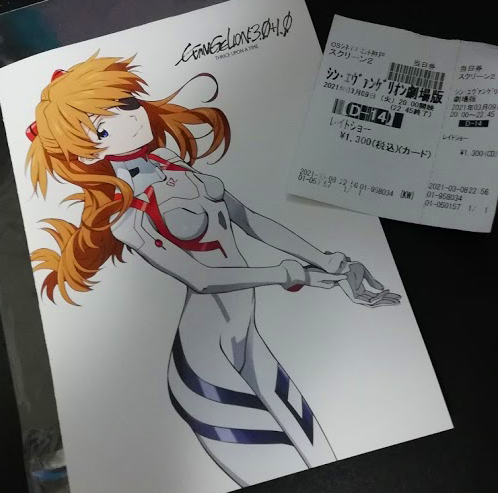
 :||
:||








